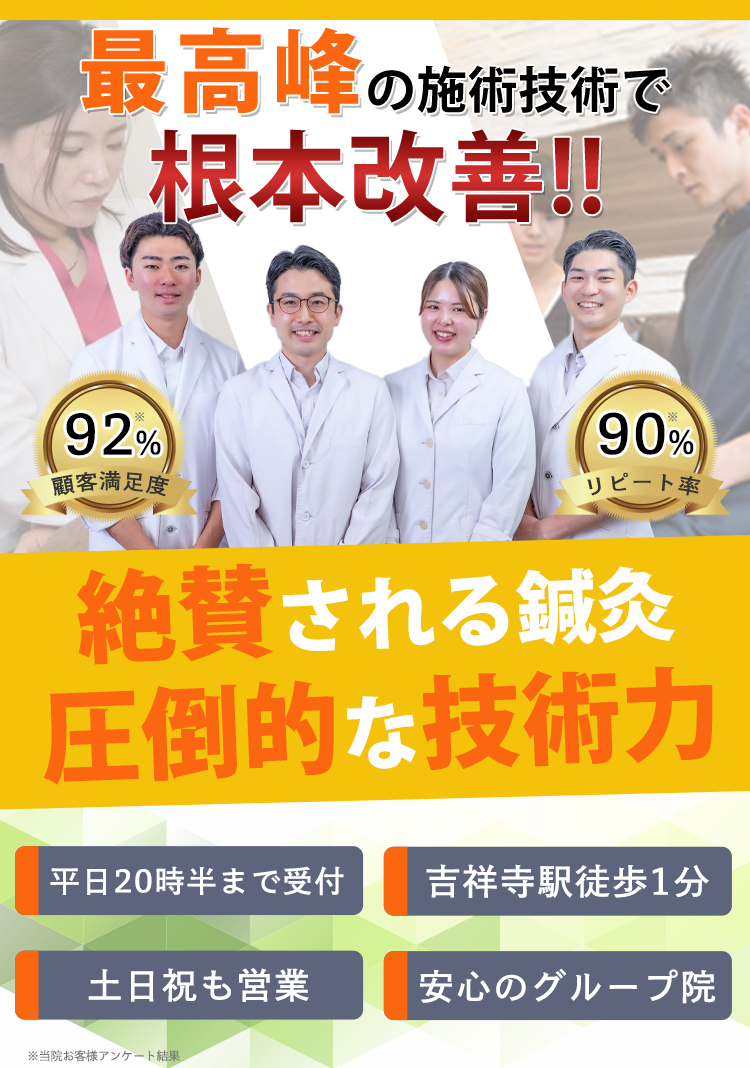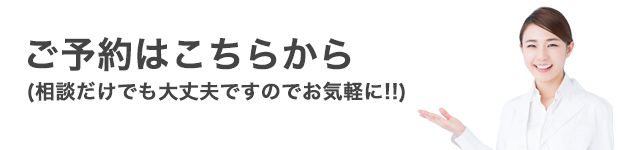副鼻腔炎とは?
副鼻腔(鼻腔の周辺にある、顔の骨の中の空洞のこと。前頭洞、篩骨洞、蝶形骨洞、上顎洞がある。)に感染、アレルギーなど何かしらの原因で生じた炎症を総称して副鼻腔炎と呼びます。
なかでも、篩骨洞と上顎洞で炎症が起きる頻度が高いです。
副鼻腔炎のほとんどが鼻炎を伴うことから、「鼻、副鼻腔炎」という名称も近年使われ始めています。副鼻腔炎は急性副鼻腔炎と慢性副鼻腔炎に分けられます。
急性副鼻腔炎は、急性に発症し1ヶ月以内に症状が消失する副鼻腔炎で、多くはかぜ症候群による副鼻腔のウイルス感染であるが、症状は軽く1週間以内に治癒します。細菌による二次感染を生じることがあり、この場合は治療を要します。
慢性副鼻腔炎は発症から3ヶ月以上症状が持続する副鼻腔炎です。鼻茸(はなたけ)と呼ばれるポリープ状のものの併発が多いことも特徴の一つです。急性副鼻腔炎が契機となって生じた細菌感染を原因とし、上顎洞での病変が多いです。従来型の副鼻腔炎が主体であります。
副鼻腔炎で生じる一般的な症状
・頭痛、頭重感
局所の疼痛や圧迫感、鼻閉による呼吸障害などによる頭重感や頭痛の症状が見られます。
・局所の疼痛、圧迫感
頬部(上顎洞)・鼻根部(篩骨洞)・前頭部(前頭洞)・後頭部や眼球後部(蝶形骨洞)に疼痛や圧迫感が見られます。また、各部の圧痛や叩打痛も見られることがあります。
・鼻閉
鼻粘膜の腫脹、鼻漏、鼻茸の存在などにより鼻孔から鼻腔にかけて狭くなったり、閉塞が生じます。
・鼻漏
鼻汁(鼻水)の病的な増加のことで、症状は様々だが粘性、膿性が多く、鼻腔内の漏出部位により、どの洞からの流出なのかを推測することができます。
後鼻漏は上顎洞、篩骨洞、蝶形骨洞で起こる炎症の時に見られることが多いです。
・嗅覚障害
鼻粘膜の腫脹、鼻漏、鼻茸などにより、嗅粘膜への通気が障害されて起こります。慢性化すると嗅神経性嗅覚障害も見られます。篩骨洞で起こる炎症の時に多く見られます。
病院での検査と処置
鼻の中の検査
鼻鏡(びきょう)や内視鏡を使って、鼻の中を観察します。
鼻の中が腫れていたりしないかどうか、鼻水はサラサラかドロドロか、鼻茸があるかないかなどを調べます。
治りにくい慢性副鼻腔炎の確実な診断のためには内視鏡検査が必要です。内視鏡は見えにくい場所の状態を見ることができるので、鼻茸が詰まっている部分を詳しく知ることができます。
必要であれば、画像検査や血液検査、嗅覚検査なども行うことがあります。
処置
① 抗生物質 (抗菌薬:細菌を抑えるお薬です)
② マクロライド系抗生物質 (殺菌作用は弱いので化膿止めではなく、免疫賦活剤として使用するお薬です)
③ 点鼻薬 (アレルギー反応や炎症を抑える効果、水分を調節する効果などいろいろな効果を持つお薬です)
④ ロイコトリエン受容体抗菌薬 (ロイコトリエンとは、体の中でアレルギーや炎症反応を起こし続ける働きがあり、ロイコトリエンがアレルギーや炎症反応を起こし続けないようにし、炎症を抑える効果を持つお薬です)
⑤ ネブライザー療法 (ネブライザーとは霧状にした薬液を鼻や喉に噴霧して、直接患部に送り届ける医療機器です)
⑥ Bスポット治療 (鼻の奥にあるBスポットと呼ばれる領域を支配することで、慢性的な鼻詰まりや副鼻腔炎の症状を軽減する治療法です)
鍼灸治療について
東洋医学に基づく治療
急性および慢性副鼻腔炎のことを東洋医学では鼻淵(びえん)と言います。
副鼻腔炎では「肝胆」「脾胃」「肺」の5つが関係しています。
・肝胆が影響している場合
辛いものを偏食したり飲酒の習慣がある方は、湿熱が体内にこもりやすく、また情志の失調(感情が過度になった状態)により肝胆の疏泄作用(気や血、体液を体全体にスムーズに巡らせ、調節する機能)が失調すると、これが肝胆の鬱熱(ストレスで心と体に熱がこもった状態)となり脳につよいダメージを与え、強い興奮で自律神経が乱れ鼻淵が起こると考えられています。
治療穴として用いられるのは、太衝、行間、丘墟、風池などがあります。
・脾胃が影響している場合
甘いものや油っこいものを偏食していると体に湿熱がこもりやすく、この湿熱は脾胃に影響しやすいと考えられています。このため脾の運化機能(摂取した食物を消化吸収し、栄養を全身に運ぶ機能)が悪くなり、清気(清らかなエネルギー)が昇らず濁陰(体内の余分な水分や老廃物)が降りなくなり、湿熱が鼻に影響すると鼻淵が起こる
また、飲食不節や過労などにより脾胃を損傷し、そのため気血の生成が不足し、また清陽(体内に存在する陽気のこと)が頭顔面部に昇らず、鼻が気血の栄養を充分に受け入れられないと邪毒(病気などを引き起こす邪気)が停滞して鼻淵が起こる
治療穴として用いられるのは、陰陵泉、内庭、中脘、曲池、合谷などがあります。
・肺が影響している場合
肺の気が不足してしまうと、治節機能(体の機能や状態を管理、調節する機能)も悪くなり、邪毒が停滞しやすくなり、それが鼻に影響すると鼻淵が起こると考えられています。
治療穴として用いられるのは、太淵、肺兪、合谷、足三里、脾兪、陰陵泉、太白などがあります。
西洋医学に基づく治療
鍼灸治療により、鼻閉の改善、鼻汁の軽減、鼻腔通気度の改善、抗炎症作用などの改善をしていきます。
治療穴として用いられるのは、印堂(いんどう)、合谷、迎香、列欠、上迎香(鼻通)などがあり鼻周りのツボを使用します。
当院の鍼灸治療
副鼻腔炎の治療では、まず免疫力を上げることが重要です。そのためには全身の血液の循環を良くすることと自律神経の状態を正常に戻すことが重要です。
血流の流れを滞らせる(冷え性やむくみ、肥満につながる)
ストレス
寒暖差
などの症状が自律神経のバランスが乱れることで見られます。
それは、鼻水が出やすくなることにも繋がります。
自律神経のバランスが乱れていると、全身の血液循環が悪くなり、血液がドロドロになります。そして血液が末梢まで流れないことで、代謝が悪くなります。
自律神経の活動を高めて免疫力を上げることが、副鼻腔炎の症状改善に欠かせないです。
副鼻腔炎にお悩みの方は、吉祥寺αはりきゅう院にご相談ください。